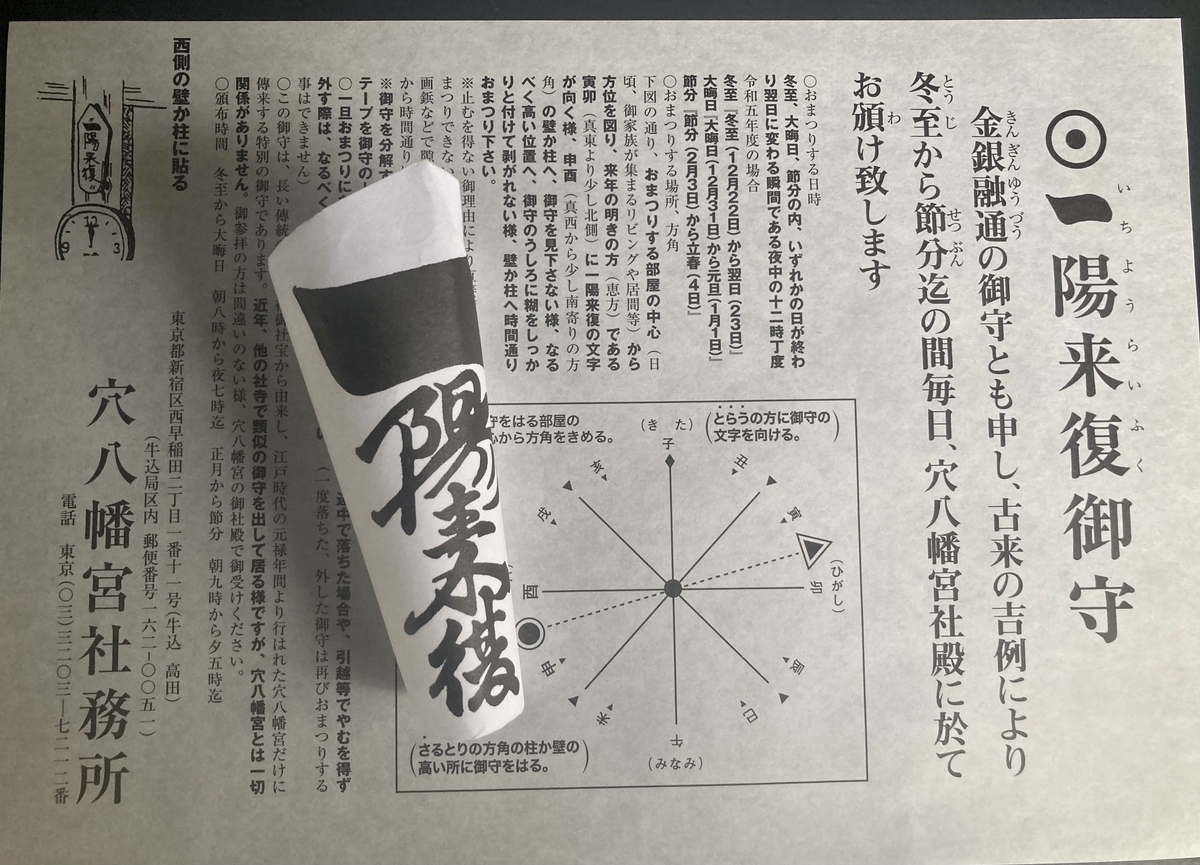脚本:游珮芸
絵:周見信
訳:倉本知明
出版社:岩波書店
舞台:台湾
出版年:2022年〜2023年
ISBN:978-4000615457 他
この作品は全4巻のシリーズ。児童雑誌を創刊するなど、台湾の文化発展に大きく貢献した蔡焜霖(サイ コウリン)氏の伝記グラフィックノベルだ。
読み終えて感じたことはいろいろある。行き過ぎた権威主義のもとで、ふつうの家族がひきさかれていく様子がつらいと思ったり、三つの言語が飛び交う焜霖の日常生活に触れ、同化政策について考えるきっかけになったりした。当時、厳しい言論統制が行われていたことを知った今、この作品を読めていることがすごいとおもった。今がありがたいというわけでは、ない。今語ってくれようとした焜霖の思いに心揺さぶられたのだ。
本来、文化も言語も、だれかに指示されて選ぶものではないはずだ。こんな過酷な状況にあったらアイデンティティが揺らいでしまう。でも焜霖はその揺らぎの中で常に前向きで、自分をなくすことがなかった。焜霖は実直で読書好きで、勉強熱心な少年だ。ただ黙って規則に従うだけではなく、自由な思想を失うことはなかった。理不尽に怒られれば心の中で抵抗することもあった。ここが大切なのではないかと思った。
1巻では自分が頭を整理したい思いがあり、歴史上の出来事も交えようと思う。1巻の紹介だけ少し長めだ。
1巻 日本統治下の台湾で生まれた焜霖、20歳までの日々を描く。
1895 年、下関条約で「台湾、澎湖諸島の日本への割譲」(『改訂版 世界史用語集』 山川出版社 2022年)が決まった。台湾は日本に統治される。
1930年、百貨店を営む裕福な一家に焜霖は生まれる。学校で教わる「国語」は日本語なので、幼少期から日本の童謡や童話に親しんでいた。家では台湾語を使っている。はじめての甘酸っぱい思い出は、幼稚園の頃、初恋のきみこと一緒に、童謡『靴が鳴る』を歌いながら、先生から通ってはいけないと言われた道を歩いたことだ。そのせいで大好きな先生に怒られ胸をいためる。先生はきみこの母親だ。「あんたの娘に誘われたんだけどな」と心の中で思いながら焜霖は怒られるのだった。
焜霖が童謡『赤トンボ』を歌っていると、兄が図書館に連れて行ってくれた。本の中ではじめてトンボの姿を知る。それ以来、好奇心を刺激する図書館が好きになる。
1941年12月、太平洋戦争が始まる。1943年、焜霖は、優秀な生徒が通う台中一中に進学した。授業以外に軍事訓練を受け、深夜行軍の演習をしたり、飛行場の草むしりなどの労働を通して軍の一員になっていく。焜霖は教えにまじめに取りくんだ。1945年、焜霖は陸軍少年飛行兵になる。1945年4月、戦況がさらに厳しくなり配給制度が開始される。政府は民間物資を買い上げ、父の百貨店は閉店を余儀なくされた。国民学校初等科以外の学校で、すべての授業が中止になる。焜霖も、15歳に満たないのに体も細いのに、学徒兵として徴用された。1945年、終戦。日本から中華民国に台湾が返還された。
「国語」は日本語から北京語に変わった。授業は再開され、焜霖は高等部に進んだ。焜霖は、すでにトマス・カーライルの本を日本語訳で読むほど、熱い読書家になっていた。スイス人のペスタロッチに憧れ、先生になることが将来の夢になった。この時、王先生と出会った。王先生は焜霖が本好きだと気づき、読書会に誘ってくれた。
1949年、中華人民共和国、建国。台湾とは、海峡を挟み、長い対立状態に入る。台湾の民衆は上から厳しい弾圧を受けていた。焜霖は映画会社に勤務する元同級生が捕まったと耳にする。「反乱分子」が密告される監視社会になっていた。やがて焜霖も連行されてしまう。読書会に参加しただけで。
絵は、淡い2色遣いの鉛筆画でほのぼのしたタッチで描かれている。日本の漫画に影響を受けただろう画風がしみじみする。気に入っているのは、焜霖ときみこのはじめての冒険を描いたシーンだ。焜霖は、近所の犬に吠えられたら、きみこを守ってあげようと思いながら、禁じられた道を歩く。農家のおじさんにさとうきびを分けてもらい、それをかじりながら『靴が鳴る』を歌う姿は、本当に小鳥のようにかわいい。1巻では、20歳までの出来事が描かれていて、幼少期の回想シーンにはあたたかい気持ちになる。焜霖が5歳の時、歳の離れた姉が結婚して家を出たのを悲しんだこと。しばらくして姉が帰省すると聞いてそわそわし、姉夫婦が姿を見せれば旦那さんにあっかんべーをしたこと。兄弟みんなで家の手伝いをするのが楽しかったこと。すべて焜霖の大事な思い出だ。だからこそ最後のシーンの衝撃が大きい。読み終えて、また、表紙のイラストよく見てみた。爆撃機にトンボの姿を重ねてあり、なるほど、と思った。焜霖は空襲警報がなると、訓練をさぼれてよかった、とひそかに思っている。この発想が子どもらしい。さとうきび畑で空を見上げ、トンボを思う焜霖はまだあどけないのだ。また、眼鏡の奥の目は、どんな表情をしているのだろう、と想像することもできる。味わい深い絵だ。また、日本統治下の台湾で生まれ幼少期を過ごした焜霖と、それ以前の時代も知っている父とでは、社会情勢の受けとめかたが少し違うのも印象に残った。
2巻以降はネタバレにならないよう、控えめに書こうと思う。
2巻 収容所での10年。
焜霖は20歳の時、「政治犯」として強制連行された。緑島という島に送られ、そこの収容所で20代の貴重な10年を過ごす。さぞ無念だっただろうと思うが、その心の穴をこの後に原動力にしていくからすごい。何かにうちこみ、気を紛らわせなければ、やっていられなかったのだろうと思う。収容所で出会った人とのあたたかいふれあいや、やせっぽっちの焜霖がたくましくなっていくさまに引き込まれた。この巻で収容所生活が終わり、安心していたが、最後のシーンに衝撃を受け、ズーンと心が沈んだ。絵の力がそうさせるのだ。すごい迫力。絵はモノトーンの木彫り版画のようで、鋭い刃でひっかいたような傷を思わせた。この巻で、気になった人物は焜霖の弟だ。
3巻 児童雑誌『王子』創刊
「服役」は終わったが、焜霖はなかなか仕事が決まらない。役場での職歴もあり優秀なのに「黒い歴史」があるせいだ。ようやく出版社で職が見つかり、日本語から中国語への翻訳に携わった。ところが、警察につきまとわれ、社をクビになる。その後、漫画雑誌の編集者になるも、検閲のせいで制作に支障が出るようになる。その後、仲間と児童雑誌を創刊した。焜霖は、「前科」があるせいで師範学校を退学させられていたので、この雑誌を発行することで、あきらめていた先生になる夢が別の形で叶うことになる。雑誌で子どもを楽しませ、励ますことができると考えたのだ。子どもの思いに寄り添った、雑誌『王子』の創刊詩を読んで、胸が熱くなった。実際の漫画が挿入されていて、臨場感があった。
4巻、民主化の時代へ
舞台は台湾東方の太平洋上に浮かぶ離島、緑島から始まる。かつての収容所は国家人権博物館に変わり、焜霖はそこで人権ボランティアをしていて、本作の脚本を書いた游珮芸氏のインタビューを受けている。
4巻目でこの作品の誕生秘話が明かされ、最近まで真実を語ることができなかったことがわかった。そこには心情以外の理由もあったようだ。游氏によれば、国民党一党独裁の時代の教科書には、台湾の歴史すら書かれていなかったとのことだ。民主化が進み、政府がようやく、白色革命で犠牲になった人々の名誉回復、謝罪や賠償、真相解明を行うようになったという。焜霖の有罪判決は2018年に無効になった。つい最近のことなのだと思うと驚くばかりだった。
まとめ
わたしは自由を求めて抗う人に惹かれるところがある。抗い方にはいろいろな方法があると思っていて、たとえば、筆をとるなどして静かな抵抗をする人たちに敬意を覚えることが多い。この作品には漫画家がたくさん登場する。台湾の独自の文化を守るためだったり、人々の癒しになればという思いだったりで、思想統制下でも娯楽をたやすまいとした漫画家たちだ。
焜霖は台湾で、児童雑誌『王子』を創刊した。文章だけではなく挿絵や四コマ漫画を加えることで子どもたちを楽しませた。雑誌は若手漫画家たちの発表の場にもなり、漫画家たちの育成も行った。また、自分の会社に同じ「前科」を持った人たちを雇用し、困っている人たちに善意の手を差し伸べてきた。その志に触れ、本当の公益とは、豊かさとは何かを考えずにいられなかった。
焜霖が本好きであることが、シリーズを通して肝心だったと思う。作中の焜霖の台詞は、声に出す時と心の中にとどめる時とがある。口に出さないからといって自分の考えがないわけではないと仄めかしているのだろう。その、ぶれない軸は、幼少期からなじんだ娯楽からつくられた。読み物だけではなく、童話や漫画、童謡などに親しんだから、精神的な糧があったのだ。それは、家族に愛されながら育てた糧でもあった。だから、厳しい統制にあっても焜霖は心の自由を完全にあけわたす事はなかったのだ。
そして、もう一人の主役は、妻のきみこだ。きみこが焜霖にとってどれだけ支えになっていたか。それに、1巻〜4巻でそれぞれ絵のタッチを全て変えてあるのも魅力だ。それがわかると、また1巻から読み返したくなる。